---The Social and Environmental Impact of Tourism with special reference to Malaysia
By CONSUMER'S ASSOCIATION OF PENANG, 1985.
ペナン消費者協会が出している小冊子です。
言葉の世界、技(わざ)の世界
山頭火の句は自画像である。
句を1枚の紙に貼り合わせていくと、山頭火の全体像が浮かびあがってくる。
句は山頭火にとって自己表現の手段である。
読者にとっては鏡であり、読み手次第で、大きく反射したり小さく答えたり、明るくもなり暗くなったりもする。
Webページは、句に変わって、Webマスターの自画像でもある。
メインテーマがビジネスでもデザインでも音楽でも文学哲学でも、それぞれの個人が自己表現をし、Web(クモの巣)状にリンクする。
Webページは、Webマスターの生存中のみ存在し、死すればWebページも消滅していく生き物でもある。
Webページが、句などの表現方法と異なる大きな一点は、扉をたたけば答えるメールによる双方向の対話だけでなく、さらに、掲示板等のツールにより、会議や討論も可能にする。
インターネットやパソコンに関わるほとんどの人は言葉や数字の抽象的な次元で生きている。
一見するとインターネットが世界をカバーするように思えても、それに抱え込まれない大きなフィールドがある。
言語で表現できない技術的なものに生きる職人やさまざまな現場に生きる人の世界もまた同じくらい広い領域を世界に占めている。
職人は物言わぬ、言葉のない腕一本の世界。
そんな世界を、言語で表現できる世界に取り込もうというあつかましいような意図も存在するようだ。
リンク→
知識創造企業
職人の世界
(職人としての経験から)
職人は、教えない。
技は盗むものという。
職人は、教えることもできない。
教えられた経験がないから。
言葉でもって教えるということは、すでに自分の中で、暗黙知を形式知におきかえる作業をしているということだ。
それをするには、形式知そのものに慣れている必要がある。
ちょうど職人が道具を駆使するように、言葉も扱えなければならない。
しかし、そんな訓練をしたことがないので、無理なのである。
「頭の人」は、決まったやり方があるように考えて、それを学ぼうとする。
農業は毎年一年生と云われるが、条件は常に異なる、ということでもある。
農業に限らない、現場の仕事とは常に1回きりなのである。
「すべての場合」をあらかじめ学習することは不可能だし、学習しても、現場では応用できずに失敗を繰り返す。
それは、結局職人が現場で技を身につけていくのと同じことになってしまう。
職人がよく言う、「技の極みはない。一生が勉強だ。」というのはそういうことでもある。
細野晴臣氏が、「その場でしかできない音楽」というのをやっていると言っていたが、人生も、それぞれの個人にとって、「その場でしかできない」ものであり、仕事も、「その場でしかできない」ものであると思う。
その場で最善を尽くし、条件とマッチしていい出来になることもあれば、その反対の場合もある。
果たして、暗黙知を形式知におきかえる作業がどれほど重要なのか、疑問に思う。
その場限りの人生と人生、その場限りの人生と場、その場限りの人生と時、それぞれのぶつかり合いの一回限りの歴史でいい。また、それ以上のことはできない。暗黙知を形式知におきかえている間に、時代は遥か彼方に行ってしまっているだろう。
(2000.6.記)
「科学」:「自然」の関係は、上に述べた、「形式知」:「暗黙知を含めた職人などの体を使う仕事や肉体労働、あるいは人間の自律神経による生命活動」の関係に対応している。
今西錦司は、知れば知るほど己の無知を自覚する、科学が進歩すればするほど科学は自然に比べて微細な存在であることを痛感される、というような意味のことを言っていたと思う。
極論すれば、何も知らなくても生きれる。直感だけで生きれるように人間は作られている。
知とか、科学とかに熱心な人は、ともすれば、知や科学は人間活動のごく一部であることを忘れ、むしろ人間活動、ひいては自然全体にまで、その守備範囲を押し広げようとするかのようだ。
極端に言わせてもらえば、これらの人は、概して体の使い方をよく知らない。訓練がない。手足が動かず、五感がフルに回転せず、自然と人間の回路が切断されている。知を重んずるあまり、体や五感の開発・訓練の体験がない。簡単に言えば、自然音痴で、不器用だ。
こういう人が頭で理解した暗黙知について語っても、それを体で知っている人が聞けば、皮相なだけで、本当に知ってはいないことが見え見えである。
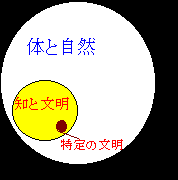
逆転してるのである。本当は、
体と自然がベースなのだが、我々には生まれた時から知と文明が用意され、そこでの一部の生き方への選択を余儀なくされている。 これが、文化というものをもつ人間と動物との違いであるといわれる。
でも、こうした歴史の流れが正しい選択であったのかどうか、ふと疑問に思うことがある。
それとも唯一必然の歴史なのだろうか?
ルソーやロックが論じた「自然状態」における人間のあり方に立ち帰って、もっと自然の大きさを知り、自然と人間の関係のあり方の多様な可能性をいつもどこかで振り返っていくことは大事だと思う。
読書やインターネット漬けでなく、体を使って自然そのものに触れることによる遊びや仕事を、もっともっと重要視しなければならないと思う。
パソコンが使えるだけで生きていけるというのは、人間というハードを極めて限定した使い方しかしていないことだし、人工的な環境だけで暮らしていくというのは、大自然があまりにももったいない。(体の不自由な方にはすみません。)
現在、世界のグローバル化ということがよく取り上げられる。
それは、文明装置の中でも、次第に特定の国の文明装置に世界が組み込まれていく、ということでもあるだろう。
ドル、英語、原子力エネルギー、等々、多様であった手段がこれらのキーワードに収斂していく。
人間の歴史は、多様な生き方が限りなく特定の生き方に収斂していく過程とも取れる。
服か着物か、薪か石油か、東洋医学か西洋医学か、…それぞれの曲がり角で一方を選択してきた。
この一方で、その本流に乗れないで、脱落していく人たちがいる。
学校での落ちこぼれ、都会生活に馴染めない人、抵抗力のない少数民族、傍流の思想や宗教を信奉する人、…まるで、トーナメントで一方が脱落していき、最後の勝者が世界の規範となる地位を得るかのようだ。
こうした環境での「賢い生き方」は、本流において、出きるだけ安定した大船に乗っていくことだろう。
すばやく現代を仕切る価値観を察知し、すみやかに学歴、英語、パソコン、ビジネスに習熟することだ。
哲学的に根底から生き方を問う、なんてことをしていたら、乗り遅れてしまう。
未開人のような自給自足を望んでいても、そのうちにブルドーザーで均されてしまう。
多様な社会が共存する、というのは非常に難しい。
主流は経済力・軍事力で必要なエネルギーや観光資源を世界に求め、商圏を広げようとするものであるから、中東などのエネルギー資源の豊富なところはもちろんのこと、資源の乏しい辺境でおとなしく生活している自給的な民族をも、格好の観光資源として掘り起こしていく。エネルギー資源→労働力→観光資源…と開発を進めていく。
積極的に観光地として開発しないで全く関与しないとしても、少なくともオゾン層の破壊や温暖化で間接的に影響を与えていく。
日本の片隅のどの田舎でも、もう皆同じような暮らしをするようになったのを見ても、ヒマラヤの山奥の村もやがてそのようにならないとは、決して断言できるものではない。
それが、その村自身の選択であるのか、そうさせられるのか、ならざるを得ないのか、よくわからない。
先進国から後進国と呼ばれる国を訪れる時、観光客は地元の人を哀れだと思うか? 地元の人は観光客を羨ましく思うか? それとも、反対に、観光客は地元の人の生活を羨むか? 地元の人は泰然として心は揺るがないか?
先進国と後進国とを対置すると、それは単に異文化というものではなく、たいていは、植民地時代に食いものにした側とされた側の関係であって、哀れの原因を訪問者側が作ってきたのだから、そもそも異文化の共存云々の話題対象ではないのかもしれない。
グローバル化というのが、究極的には、世界の通貨が統一されてシベリアからパタゴニアまでのすべての地域がインターネットを通じてひとつのマーケットとして商品物流し、国境がなくなり、世界の言語が統一され、すべての民族の垣根が取り払われて民族間での結婚がなされ、…というようなことをいうのか、先のことは簡単に予見できないが、もしそうだとしたら、マイノリティのそれぞれの地域における自然と人間の自然発生的な関係やそこに生じた文化といったものが消滅してしまうことは必至である。
それらは、例えばグローバル経済における一観光産業の担い手と位置付けられてしまい、そこでのかつてあったミクロコスモス的なコミュニティに代って、モノカルチャー的な観光エージェントが立ち並ぶ地域となってしまう。そして、そこの住民の生活形態は他の世界と同じようなものになってしまう。
これは文化的景観的観光資源を取り崩していくことでもあり、その観光産業自体にとって矛盾するものでもある。
同時に、その地域住民はグローバルエコノミーに左右される不安定な存在になってしまう。
身近な例でいえば、地元住民の里山として生活に欠かせない自然が、整地されてゴルフ場になって、一度は雇用の機会が増え生活レベルがアップしたと喜んでいたが、不況の波でこのようなレジャー的要素の強い産業は一番に切り捨てられていく。
それが、跡地に汚染を残さないものであればいいけれど、足尾銅山のようなものがある。
その産業が、地元住民の生活のためのものか、グローバルの要請か、この違いは環境保全の態度に如実に現れるだろう。
グローバルの要請における観光産業は、軽井沢がだめになったら清里、それがだめになったら湯布院、その次は…と、貪欲に消費していく怪物のようだ。
そのようなことを防ぎ、恒久的な資源として保存していこう、というのが、世界遺産の考え方かもしれない(もちろん観光産業のためだけではないだろうが)。でもこれも、あくまでグローバル社会に組み込まれたものとしての保存だ。
[関連図書]
![]() See the Third World while it lasts
See the Third World while it lasts
---The Social and Environmental Impact of Tourism with special reference to Malaysia
By CONSUMER'S ASSOCIATION OF PENANG, 1985.
ペナン消費者協会が出している小冊子です。
(2002.1.記)