| 12 Angry Men written by Reginald Rose | 2005.9.19〜 記 随時追加していきます 改訂:2006.8.26 |
|
| オリジナル 十二人の怒れる男 製作:1957年 監督:シドニー・ルメット 主演:ヘンリー・フォンダ 字幕:進藤光太 モノクロ 96分 |
1番マーティン・バルサム 2番ジョン・フィードラー 3番リー・J・コッブ 4番E・G・マーシャル 5番ジャック・クラグマン 6番エドワード・ビンズ 7番ジャック・ウォーデン 8番ヘンリー・フォンダ 9番ジョセフ・スウィーニー 10番エド・ベグリー 11番ジョージ・ヴォスコヴェック 12番ロバート・ウィーバー |
|
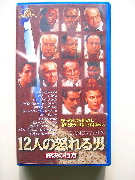 |
リメイク 12人の怒れる男――評決の行方 製作:1997年 監督:ウィリアム・フリードキン 主演:ジャック・レモン 字幕:岡田壮平 カラー 117分 吹替版翻訳:岸田恵子 |
1番コートニー・B・ヴァンス 2番オシー・デイヴィス 3番ジョージ・C・スコット 4番アーミン・ミューラー=スター 5番ドリアン・ヘアウッド 6番ジェームズ・ガンドルフィーニ 7番トニー・ダンザ 8番ジャック・レモン 9番ヒューム・クローニン 10番ミケルティ・ウィリアムソン 11番エドワード・ジェームズ・オルモス 12番ウィリアム・L・ピーターセン |
| 12 Angry Men は、私にとってNO.1映画です。 オリジナルはもう200回は見たでしょうか。 リメイクも100回ほど見ているでしょう。 |
||
| この映画の醍醐味を一言で言うと、性格劇の面白さです。 脚本は、あらためていうまでもなく、非常にすぐれています。 しかし、そのストーリーの面白さや、訴える内容よりも、ドラマの進行にしたがって次第に明らかになってくるそれぞれの個性、考え方、陪審員としての姿勢などが見所だ。 通常このような映画の場合、フラッシュバックで、その事件を再現したりしますが、それは一切なく、会話の進行に従って、見るほうに次第に明らかになるようになっています。その推理小説的な面白さもある。 また、陪審員たちの偏見や先入観で審議が歪められることがある、とかいうことを特に言いたい訳でもない。なんといっても、さまざまな個性のぶつかり合いが最大の見所である。 だから、この映画は何回リメイクされても、そのたびに楽しめるだろう。 発言している人だけでなく、周りのひとが、その発言に対して、どういう反応や表情を示すかを見るのも、面白みのひとつだ。 またそこが、役者にとってもやりがいのあるところだろう。 |
||
| オリジナルを最初に見たのは、多分、1969年頃だと思う。どこで見たのか憶えていない。そのすぐ後に、ペーパーバック(Ladder
Edition) のシナリオを買った。 リメイクを見たのは、1997年頃だが、これもどこで見たのか憶えていない。 それっきりずっと見ていなかったが、印象にのこっているので、2004年にオリジナルのビデオを買った。この年に150回は見た。 リメイクのビデオは2005年に購入して、100回ほど見ている。 まだどちらも飽きがこない。 これからも何百回も見るだろう。 非常にすぐれた作品であるので、上記 Ladder Edition に続いて、英宝社(坂本和男・編注/1975初版)から出ているシナリオも2004年に買った。(開文社からも出ているが、中身が少し違うようだ) 邦訳のシナリオも出ているが、持っていない。 Ladder Edition のものは、テレビ用のシナリオらしい。 リメイクは、英宝社のシナリオに忠実なようだ。(リメイクのほうが元のシナリオに忠実だと思える) オリジナル、リメイク共に、俳優が自分の表現に勝手に変えて言っているフシもある。撮り出したら、流れや勢いが大事なので、監督も少々の台詞の違いよりもそれを優先したのかもしれない。 本作はまず、1954年9月20日にCBSでTV放送され、1957年にワーナー・ブラザーズで映画化、1958年に舞台公演されたらしい。 それぞれのシナリオがそれぞれ上記と同じ年に書かれている。 このシナリオは、TV、映画、舞台・・と製作、上演されるごとに、練られていったものだと思う。演じる人、監督、などからも筋立てについての提案もあって、きっと採用されていることだろう。 |
||
| オリジナルとリメイクのシナリオの細かい違いについては、あとで述べる。 まず、大きな違い(私の印象)を述べます。 オリジナルとリメイクの違いで、一番気になったのは、カメラだ。 最初、オリジナルを何回か見て、まず思ったのは、定位置から撮るため、カメラを移動して、その後の続きめで、光線の具合や明るさが違っていて、雰囲気が微妙に変わること、俳優が前の場面の気分や雰囲気を持続できなくて、そこで途切れたような感じになるところが数カ所あった。これが、オリジナルの唯一の欠点といえば、欠点だ。 この欠点を多分リメイクは意識したのだろう。 自由に動くカメラ(専門用語でなんというのか知らない、誰か教えて下さい)で、流れるように撮っている。より自然な流れにはなっていると思う。 しかし、このカメラは、映画を見るものにとって、カメラを意識させ、映画そのものに没入させきれない面がある。これが、このリメイクの欠点ともいえそうだ。 どちらのカメラが良いか、といわれれば、オリジナルが良い、と言う。 リメイクはカメラの存在を意識させ、時にうるさい。俳優にとっても、急に目の前にカメラが来るので、思わずカメラと目を合わしてしまう。(バンス、スコット、ガンドルフィーニの3人) しかし、これを実際の場面を撮影しているドキュメンタリと捉えれば、別にカメラと目が合っても問題はない。 実際、目が合ったことで作品が損なわれることにはなっていない。だから勢いを優先して、撮り直しもしなかったのだろう。 もうひとつ、オリジナルのカメラの撮り方が良いと思う点は、クローズアップの多用。 表情をくっきりと見せることの他に、その場面を強調する。特に、議論で相手をやり込めた場面で功を奏している。 また、リメイクでは、この相手をやり込めるポイントで、オリジナルのような十分な間(ま)を取っていないので、初めて見た人にはその意味が見過ごされてしまう危険がある。 特に3番のスコットが2回ほど、十分な間を取ってないために、その意見の効果があまり見る者に意識されなかったのでは、と懸念する。 その相手をやりこめる意見とは、具体的にいうと、 「どうして、目撃した女性の意見を信用して、被告の意見を信用しないのか?」という8番の10番に対する発言、 「そんなに正確なこと (exact science) は誰も言えない」という8番の12番に対する発言、 「だれでも我慢できない限界 (breaking point)というものがある。」という4番の8番に対する発言、 10番の「He do not speak・・」という発言を、11番が「He dose not speak・・」とたしなめる場面、 「本当に殺すつもりではなかっただろ?」という8番の3番に対する発言、 「もうろくした年寄りの言うことなんか信用できるか」という矛盾した3番の発言、 などのあと、オリジナルは、十分な間を取っている。 リメイクでは、自然な流れを大事にしたのか、俳優に徹底されなかったのか、間がなく、聞き流してしまいそうである。 だからといって、リメイクが劣るとは、決して言えない。 フリードキンさん、よくぞ、作ってくれました、とお礼を言いたい。 これからもどんどん色んな人にリメイクを作ってもらいたい。 そのたびに、新しい十二人の怒れる男が楽しめるだろう。 |
||
| この映画には見所がいくつかある。 1. ナイフを、8番がポケットから取り出すところ オリジナルでは、フォンダが、こころなしか、どうだ見たか、という気分のためか、笑いをこらえきれないような感じがする。 2. 9番が、Not Guilty に1票入れた場面 これが、この映画が、評決逆転するまで延々と続くきっかけとなる。 3. 3番が8番に「殺してやる」と言い、8番が「本当に殺すつもりではないだろう」と言って、先の3番の「殺すと少年が言ったのはそのつもりで言った」という発言が必ずしも正しいとは言えないことを3番自身が証明しているとやり込める場面 4. スラムに育った5番が犯行に使用されたナイフの使い方は、アンダーハンドでやることをやって見せる場面 5. 7番が意見を翻して、Not Guilty に1票入れた場面で、11番が攻め寄る場面 6. 8番が、4番に、前日、前々日・・の行動を問いただして、4番も被告同様に映画のタイトルをを正しく憶えていなくて、記憶の不確かなことを確認させる場面 7. 9番が、4番の鼻のメガネ痕に気づき、女性の視力に疑問が出て、いよいよ11人が、Not Guilty に票を入れることになる場面 オリジナルでは、汗をかかないはずの4番の額に、一筋の汗が流れるクローズアップが秀逸である。 9番の観察力の良さは、先に、証人の老人の衣服について等の発言で予め知らされてある。 8. 最後の、3番のNot Guilty に変えるまでの発言場面 オリジナルでは、写真の小道具が生きている。 |
||
| 俳優 さて、オリジナルとリメイクの演技者を見てみよう。 オリジナルではなんといっても、3番のリー・J.コップである。 この人が主演といっても言い過ぎではない。 この映画で、リー・J.コップが好きになった。 どこかで聞いたことのある声だとおもったら、「セールスマンの死」のオーディオブックで主人公を演じている。舞台でも、「セールスマンの死」を長らく演じたらしい。映画「セールスマンの死」ではダスティン・ホフンマンが主演だが、リー・J.コップの主演映画を残してくれなかったのは悔やまれる。 リメイクでは、10番のミケルチ・ウィリアムソンだ。 最初見たときは、なんだこれ、ぜんぜん良くない、とおもったのだが、見ていくうちに、彼に助演賞をあげてもいいと思うようになった。 ただ、リメイクでは、なぜイスラム教徒の黒人にしてあるのか、ちょっと?である。アメリカのイスラム嫌いを反映しているとは思いたくないが・・・。 ジャック・レモンももちろんいい。特に発音が一番聞き取りやすい。 (オリジナルでは、4番のE・G・マーシャルが聞き取りやすい) スコットも賞を取っただけに良かったが、先に言った「間」の部分だけ、ちょっと不満がある。 この作品の役では、8番、3番、7番、10番、4番が重要な役割を担っている。 その他の役も、それぞれ、個性的な人材が求められる。 オリジナルでその個性を発揮したのは、7番のジャック・ウォーデンだ。 7番と12番は、この作品の味付けにとって面白い存在だが、4人とも良く演じた。 9番、11番も重要な役だが、これも4人がうまく演じてくれた。 ついでながら、マーロン・ブランド主演の「波止場」(この撮影もオリジナルと同じボリス・コーフマン)には、オリジナルの1番のマーティン・バルサム、3番のリー・J.コップ、そして、裁判長を演じた俳優がそろって出演している。 裁判長で思い出したが、オリジナルでは、裁判長は、この裁判に気が入ってない感じに撮ってあったが、リメイクの女性裁判長は妙に真面目に裁判に取り組んでいるふうで、この筋には合ってないと思った。 |
||
| ここで、シナリオにある、十二人の性格描写を見てみよう。 Ladder Edition に書かれているものを訳してみました。 1番:小さい男。気も小さい。良き議長であろうとし、その権威にまんざらでもない。特に利口ではないが、その職務をキチンと果たそうとする。 2番:穏やかな男。自分自身の意見を持つわけでなく、確たるものはない。影響されやすく、新しい意見になびいてしまう。 3番:強気で押しが強く、確たる信念をもって話す。時に自らの残酷さを楽しんでるふうでもある。ユーモアを解せず、他人の意見は受け入れず、自分の気持ちや意見を他に押し付ける。 4番:裕福そうで、一見重要な人物に見える。表現が冴え、自分の意見を的確に話す。他の陪審員よりも自分が優れていると感じている風でもある。陪審員に提供された事実だけに関心がある。他の陪審員の(感情的な)行動を良く思っていない。 5番:ごく普通のおどおどした若い青年。みんなが自分よりも年がいっているので、意見を述べにくいと感じているが、陪審員としての義務には真面目に取り組んでいる。 6番:正直ではあるが、鈍く、注意深いが、決定が遅い。自分の意見をまとめることができず、他の人の言ったことで、一番いいと思った意見になびいてしまう。 7番:うるさくて、がさつなセールスマン。もっと他にすることがあるので、陪審員として席におちついて座っていられない。怒りっぽく、何もわかっていないのに、簡単に意見を言う。他人を小物として扱いたいようであるが、内心では自分が小物であることを承知している。 8番:もの静かで、思慮深く、穏やかな男である。すべての疑問点をあらゆる角度から洗い出し、常に真実を追求する。他に対する思いやりの精神に富み、彼こそ真の強者である。特に重要な性質は、正義がまっとうされることを望み、正義の為に戦う姿勢である。 9番:おとなしい老人。昔、人生に敗北し、ただ死を待つ。自分の限界を知っている。年齢を笠に着ないで、ただもっと強く行動できるほどに若くありたいと思う。 10番:激怒しやすく不愉快な男。周りの人を敵に回す。外国人が嫌いで、自分の人生しか考えない。自分の居場所がなく、行くあてもない。それを自身も内心良く分かっている。 11番:戦争を逃れてヨーロッパからアメリカに移住してきた人物。英語が母国語ではないのが話し方で分かる。恥ずかしがりやで、周りの人の召使ともいえるような控えめさである。まともに扱われてこなかった経験から、正義を求める気持ちは本物のようだ。 12番:人当たりが良く、切れる男である。広告業界で働く。ビジネスの観点でしか人間を見ず、人間に対する真の洞察がない。他に対して優越感を持っているが、よく思われようと立ち振る舞う。 衣服:陪審員たちは、普通の夏用の仕事着を着ている。4番は明るくてカラフルな上等の服を着ており、12番はスタイリッシュでうまく着こなしている。 |
||
| 2つのシナリオ上の違い(ちょっと細かいことですが、気づいたこと) オリジナルでの11番のデモクラシーの発言が、リメイクではなくなっている。 リメイクでは、1番の精神分析医の考察についての意見があるが、オリジナルでは省略されている。 7番の野球に引っ掛けた発言が面白い。例えば、評決が6対6になった時、We go into extra innings (延長戦に入った) などという発言の他、いろいろある。また、球団の名前や、確か選手の名前も、時代に応じて変えられている。(オリジナルはボルティモア、リメイクではミルウォーキー) オリジナルでは、壁の時計が見えなかったが、リメイクでは時間がわかる。 オリジナルの扇風機が、リメイクではエアコンになっている。 そのため、例の7番の子供っぽいいたずらが、リメイクではなくなっている。 4番が見たという映画のタイトルは、オリジナルでは、The Amazing Mrs.Bainbridge、 リメイクでは「秘密と嘘」* オリジナルでは7番はしょっちゅう腕時計を見ているが。リメイクではあまり見ていない。 最後の場面。陪審員としての役割を終えて裁判所を去るシーンも注意深く観てほしい。 オリジナルでは、裁判所を出てそれぞれがそれぞれのペースでそれぞれの方向に散って帰っていく。あの蒸し暑い部屋での熱論のあと、雨が上がった爽快感の中、それまでの全く赤の他人に戻って帰っていく。8番と9番が最後に名前を名乗り合うのも、全く知らない同士であったことを確認させ、あらためてその激論に一つとなった陪審員たちと比べてしまう。 それぞれが最後まで役柄を反映した歩き方を演じている。7番ジャック・ウォーデンはもちろん急いで野球場に向った。最後に裁判所から出てきた3番リー・J・コッブは、うつむいてとぼとぼと階段を降りていく。息子のことを考えているのだろう。 リメイクでは、趣向を変えて、エレベーター前での別れ方にしている。 この前に、評決に至ってから、裁判長のところに戻っているはずであるが、オリジナル、リメイク、どちらも省略している。 「淀川長治映画ベスト1000」(河出書房新社/2000年刊)の「十二人の怒れる男」の項(P.159)では、「夜明けになって陪審員たちがフラフラになって部屋から出ていく」とあるが、これは間違いですね。何で淀川さんは徹夜で話し合ったと勘違いしたんでしょうね。終わって外に出たら明るかったからでしょうか? 夏の日没前ですね。7番が急ぎ足で出て行きました。これからナイターに行く時間です。 「淀川長治映画ベスト1000」には、この他にもおかしいところがあるようです。記憶でコメントを書いたんですね。 でも大したものですね。あの頭には映画のことがいっぱい詰まってます。 ではさいならさいならさいなら。 |
*「秘密と嘘」 監督:マイク・リー。 脚本なし。 出演:ブレンダ・ブレッシン、ティモシー・スポール。 96年カンヌ映画祭パルム・ドール、主演女優賞(シンシア・パーリー)、国際批評家連盟賞の三冠を獲得 |
|
| ******************************************************* | ||
| 「またお会いしましたね」 今回はシドニー・ルメットの作品について書いてみます。 最近立て続けにルメットの作品を見ました。 以下は彼の作品ですが、*印が私の見た作品です。 クライシス・オブ・アメリカ 男優 2004年 *グロリア(1999) 監督 1999年 *NY検事局 監督・脚本 1997年 *ギルティ/罪深き罪 監督 1993年 *刑事エデン/追跡者 監督 1992年 *Q&A 監督・脚本 1990年 *ファミリービジネス 監督 1989年 *旅立ちの時 監督 1988年 *モーニングアフター 監督 1986年 *キングの報酬 監督 1986年 ガルボトーク/夢のつづきは夢・・・ 監督 1984年 ダニエル 監督 1983年 *デストラップ・死の罠 監督 1982年 *評決 監督 1982年 *プリンス・オブ・シティ 監督・脚本 1981年 ジャスト・テル・ミー・ホワット・ユー・ウォント 監督 1980年 *ウィズ 監督 1978年 エクウス 監督 1977年 *ネットワーク 監督 1976年 *狼たちの午後 監督 1974年 ラヴィン・モーリー 監督 1974年 *オリエント急行殺人事件 監督 1974年 *セルピコ 監督 1973年 オフェンス 監督 1972年 チャイルズ・プレイ 監督 1972年 ショーン・コネリー/盗聴作戦 監督 1971年 約束 監督 1969年 ラスト・オブ・ザ・ホット・ショッツ 監督 1969年 バイバイ・ブレイバーマン 監督 1968年 シーガル 監督 1968年 デッドリー・アフェア 監督 1967年 グループ 監督 1966年 丘 監督 1965年 *質屋 監督 1965年 *未知への飛行 フェイル・セイフ 監督・製作総指揮 1964年 ロング・ジャーニー・イントゥ・ナイト 監督 1962年 橋からの眺め 監督 1962年 蛇皮の服を着た男 監督 1959年 私はそんな女 監督 1959年 女優志願 監督 1958年怒っているのか、 *十二人の怒れる男 監督 1957年 TVドラマでは、ジャック・レモンの「デンジャー」等があります。 他に、「ザ・ディレクターズ シドニー・ルメット」(東北新社/1997年/59分)という、インタビュービデオを見ました。 さて、作品についてですが、「十二人の怒れる男」が飛び抜けているだけに、大したものはないという感じです。 ただ、「刑事エデン/追跡者」だけは拾い物でした。アーミッシュの世界が舞台になっています。これは好きな作品です。 「未知への飛行」は、キューブリックの「博士の異常な愛情」同様それほど強い印象はありません。 ホロコーストがテーマの「質屋」は、35年以上前に見たので覚えていません。 ルメットの作品に共通しているというか、繰り返し出てくるテーマは、「ユダヤ人」、「警察の腐敗」です。 |
||
| 2007.07.18記 当ホームページに、「陪審員 それぞれの怒り」のキーワードで検索してアクセスしてきた方がありました。 タイトルに“Angry”がついているので、各陪審員が、何に、あるいは、どう怒っているのかあらためて考えてみました。 1番:彼が怒ったのは、1回ほどしかない。概して穏やかな男だ。10番に進め方について非難され、子供っぽいと言われたとき、「じゃあ、お前が司会をやれ!」と言い返した。 2番:おとなしい男なので、あまり怒ることはない。10番に、のど飴がないか、と言われたとき、むっとしたように、「もうない」と言い放った。それと、リメイクで、やはり10番に、「なぜ意見を変えた。・・白人の言いなりになっているんじゃねぇ」と言われた時、“loud mouth”(口の悪い奴だ)と、立ち去った10番の背中を追うように言葉を浴びせた。 3番:10番と共に、いちばん怒った男である。10番は後半に4番から、「黙ってろ!」と言われてからほとんど発言の機会がなかったので、最後まで怒り通した3番は怒れる男の筆頭株である。ただ最後には「改心」して、誤っていたことに気づき、認め、意見を翻したので、10番のように救いようのないという男ではない。この3番の怒りは、実は自分の息子に対して向けられていたものであるが、被告の若い男にオーバーラップして、その怒りが被告に向けられた。感情的なものが先立っていたので、頭から被告を有罪と決めつけ、何かにつけ怒鳴りつけた。 4番:冷静に考え、理路整然とした意見を言う。例えば、12番が、有罪から無罪に意見を変えた時、その根拠を問うた。言うべき事は言い、しかし終始感情を露にすることはない。皆が感情的に叫んだりするのを嗜めるだけである。 5番:8番の提案で最初に無記名投票した時、3番に、「無罪に入れたのはお前だろう」と誤解された時に怒った。7番に食ってかかったこともある。 6番:3番が9番に礼儀知らずな暴言を吐いた時、「もう一度そのような口をきいたらぶっ飛ばしてやる」と怒った。 7番:野球のナイターのことで頭がいっぱいで常にいらいらしている。裁判については考える意欲も能力もないので、議論で勝つ勝たないのために丁々発止渡り合う過程での、怒りを露にするだけの意見もない。まともに意見を戦わせて発言することはできないので、いつも軽口をたたいて時間をやり過ごしているといってもよい。早く切り上げたいので、無罪に意見を変えたところを11番に咎められ、詰め寄られても、その怒りは萎んでしまうだけだ。その後も軽口をたたき、最後にはナイター会場に駆けて行った(オリジナル)。 8番:理性的な男である。怒ることは少ないこの正義漢が怒ったのは、3番に対して「サディスト!」と言った時くらいであろうか。正当な審議を被告に対して望んだのは、人間的道義的な心情からであり、その根底には特に怒りはない。 9番:年寄り相応に控えめであるので、そんなに怒る場面はない。オリジナルでは、目撃証人の女性の鼻にある眼鏡の痕についての発言の際、3番が、また何を言い出すかこのじじい、とばかりに口を挟んできた時に、キッとして、今4番に大事なことを話そうとしているのだと3番の口を封じた。 10番:常に怒っている。7番同様、こんな裁判に時間を取られるのは無駄なことだと思っている。スラムに住むヒスパニックに対する偏見が基底にあり、口汚く罵り、他の陪審員をも敵に回し、皆の反感を買って、逆に11人の怒りが10番に向かう。 11番:控え目ではあるが、根が生真面目であるので、さすがに7番が無罪にした時には我慢がならず、怒りをもって詰問した。 12番:この男も裁判のことより、自分のビジネスのことが頭にあって、陪審員としての責務にもやや消極的だ。3番から、テニスボールのように意見が行ったり来たりすると非難されるが、空気が読めないほどバカではない。他人の評価を気にするこの男は、自分のいい加減さをちょっとは反省したのか、オリジナルの最後のキャスティング紹介のところで、陽気な冗談屋の12番を、ロバート・ウィーバーは、やや暗い浮かない顔で締めくくっている。 |
||
| 英語で映画 映画で英語 | ||
| このページは、ヒマラヤン・シェルパ・アドベンチャー が提供しています。 | by morisaki | |